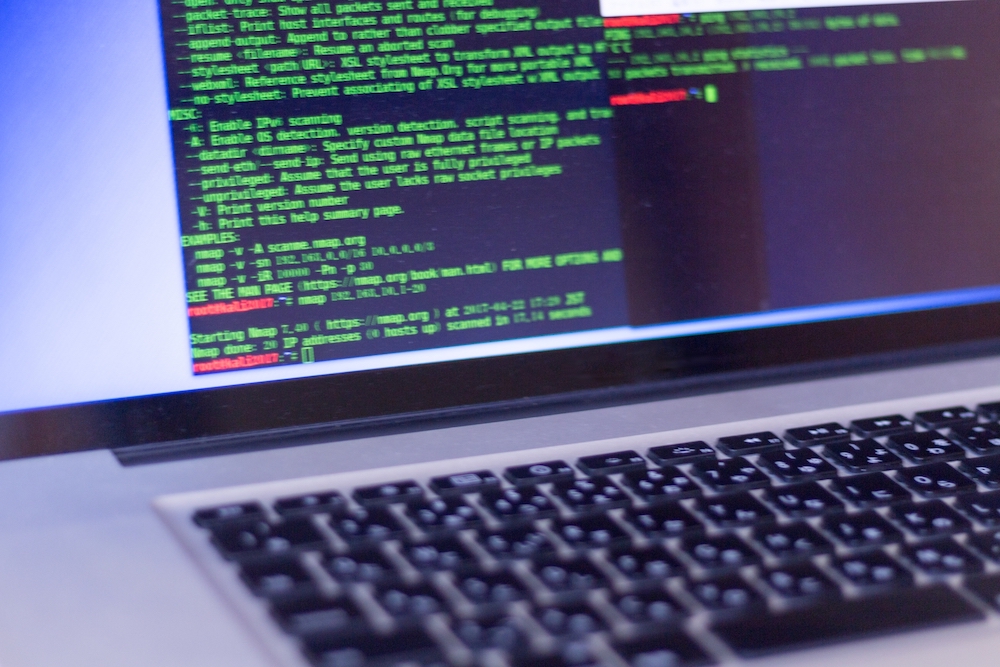企業におけるPLMとはProduct Lifecycle Managementの略語で、製品ライフサイクル管理と呼ぶことができます。
これは、何らかの製品、商品を作ることを仕事としている企業において、そのライフサイクルを管理し、最終的には売上高の最大化とか利益を最大化を目指すことを目的としています。
製品や商品と一口に言ってもその種類は実に様々であり、ノートや鉛筆のような文具もあればテレビやパソコンのような家電製品もあります。
業界によってPLMの姿は大きく異なる
自動車などももちろんそうですし、一般の消費者を対象にするわけではないものの例えば工場で使うような機械設備を製造することを仕事にしている企業もあるでしょう。
業界によってPLMの姿は大きく異なるでしょうが、一般化して話すことは可能です。
おそらくどんな製品であっても、まずはどんなものを作れば良いのか、どんなものが顧客のニーズに合い、売れると見込まれるのかという企画段階からスタートするでしょう。
企画が固まれば、次は具体的にどのようにすれば作ることができるのか、その設計を考えることになります。
設計図ができれば、実際に製造することになるでしょう。
もちろん多数の製品を作るよりも前に試作品のようなものを作ることもあるでしょうが、それは細かい話です。
製造しさえすれば後は販売するだけかというと、なかなかそのような簡単な話ではないことも多いはずです。
もちろん製造後に販売が来ることは間違いないでしょうが、高度な技術力を必要とするような製品であればあるほど、販売だけのことを考えていれば良いわけではなく、例えばメンテナンスであるとか、バージョンアップ、マイナーチェンジといったアフターケアも大事になってくるでしょう。
企画、設計、製造、販売、アフターケア、廃棄という一連の流れがPLMの代表例
そして、同様に高度化した製品であればあるほど、寿命が来て使えなくなった後の回収とか廃棄、リサイクルなどについても責任を持つことが企業として求められるのは今や当たり前の時代です。
このように、企画、設計、製造、販売、アフターケア、廃棄という一連の流れがまさにPLMの代表例ということになるわけです。
こう考えると、別にPLMは非常に新しい概念でも発想でも何でもありません。
製造業という企業が生まれたのと同時に基本的な考え方そのものは生まれていたはずと言えるでしょう。
もっと言えば、別に企業活動としてであることさえも必須ではなく、顧客に購入してもらうことを目的としているのであれば個人的に製品を作るケースであっても該当する考え方のはずです。
ですが、考え方そのものは別に新しいものではなくても、最近になって特に注目されていることは事実でしょう。
その理由にはいろいろあるでしょうが、世の中の動きが早くなり、海外も含めてライバルも多くなって、PLMをしっかりと行っていかないとなかなか売上げや利益が上がらないというか、PLMをしっかりと行うことで無駄な仕事を省き、売上げや利益につながることが分かってきたからということができます。
PLMの必要性と実態について
そういう意味では、昔からほとんど製品の本質は変わっておらず、何十年も同じ製品を作り続けて安定的に販売しているようなケースではPLMをゼロから取り入れるような必要性はあまりないでしょう。
単なるノートや鉛筆といった製品について、いちいちゼロベースで、さて次はどんなノートを作るのが顧客のニーズに合っているのかと担当者全員が雁首揃えて考えたり、設計図をゼロから書き起こすようなことはやはりちょっと変です。
このような製品については、そのようなことをあまり考えることなく従来通りに作って従来どおりに販売するのが最適な戦略であることも多く、PLMを取り入れることでかえって無駄な時間やコストを要することも多いでしょう。
ただ、以前とは異なって今ではPLMの各段階において種々の情報が電子化されているか電子化可能なことが多く、紙情報がメインであった時代に比べれば、それらの統合が比較的簡単に達成できることも多くなっています。
これにより、ライフサイクル上のあるポイントでの何らかの情報によって、それが別のポイントでどのように影響してくるのかを一元的に管理したり把握したりすることが昔に比べて容易になってきており、それだけPLMの導入のハードルが下がってきているというか、PLM導入によりメリットを出すことが行いやすくなってきています。
まとめ
とはいっても、一般論として言えば、PLMを取り入れるのが役立つと思われる製品とは製造そのものも含めてライフサイクル全体が複雑で長期にわたるようなものとか、顧客のニーズの変化が激しかったりトレンドが変わることが多かったりして、必要に応じて素早く製品のライフサイクル全体を見直すことが求められるような製品、そしてもちろんある程度以上に商品単価が高く、PLMを取り入れることに要するコストを十分に吸収できると思われるような製品ということになるでしょう。
最終更新日 2025年6月10日